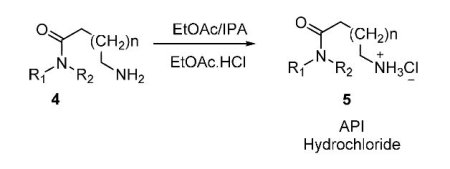Advertisements
1)粘土の一軸圧縮強さqu(kN/m2)
2)粘土の粘着力cu(kN/m2)
3)砂の内部摩擦角φ(°)
4)変形係数E(kN/m2)
5)地盤のS波速度Vs(m/s)→地盤の基本固有周期(地盤種別と構造物の共振検討)
6)繰り返しせん断強度→液状化判定
岩盤の場合では単位体積重量の設定に使ったりもします。
6)繰り返しせん断強度→液状化判定
岩盤の場合では単位体積重量の設定に使ったりもします。
地層区分するときに重要な手がかりになりますし、非常に役に立つ試験値ですね?
これらのN値による推定値は、対象とする構造物によって設計基準があり、設計基準ごとに算定式
が異なります。なぜなんでしょう??
というか、地層区分とか硬軟の把握以外の用途で使うのは、本来ダメだと思っています。
(データが何もない場合には目安値としては有効ですが、設計値としては信じてはいけません)
これらのN値による推定値は、対象とする構造物によって設計基準があり、設計基準ごとに算定式
が異なります。なぜなんでしょう??
というか、地層区分とか硬軟の把握以外の用途で使うのは、本来ダメだと思っています。
(データが何もない場合には目安値としては有効ですが、設計値としては信じてはいけません)
変形係数E(kN/m2)
吉中は、N値と孔内載荷試験結果から求めた変形係数EPとの関係が土質を問わず、
EP=678・N^0.9985≒700・N(kN/m2)が成り立つことを示しました。一般にこの関係式が使われます。
一方、地盤反力係数を求めるときに用いる地盤の変形係数ESは、想定している変形量が微小であることからEPの3~4倍の値となってます(平板載荷試験結果との関係です)。
言葉では同じ変形係数ですので、混同しないよう留意する必要があります。
EP=678・N^0.9985≒700・N(kN/m2)が成り立つことを示しました。一般にこの関係式が使われます。
一方、地盤反力係数を求めるときに用いる地盤の変形係数ESは、想定している変形量が微小であることからEPの3~4倍の値となってます(平板載荷試験結果との関係です)。
言葉では同じ変形係数ですので、混同しないよう留意する必要があります。
・孔内載荷試験との相関(吉中)
Ep=700・N
・道路橋示方書(地盤反力係数計算)
ES=2,800・N
・鉄道構造等設計基準
ES=2,500・N
・建築基礎構造設計指針
ES=2,800・N (過圧密の砂、地下水面以浅)
ES=1,400・N (正規圧密の砂、地下水面以浅)
建築基礎構造設計指針での正規圧密の砂のES=1,400・Nが要注意です。
建築基礎構造設計指針での正規圧密の砂のES=1,400・Nが要注意です。
せん断波速度Vs(m/s)
せん断波速度Vsは、せん断剛性や変形係数を算出する定数として利用されます。また、地盤の基本固有周期TGを求めるためにも使われます。Vsは、PS検層から求めることが望ましいですが、N値からも関係式から推定するすることが出来ます。
TGから調査地点における耐震設計上の地盤種別を決定します。したがってTGは地震加速度、地震時せん断応力比等に影響する値であり、それをN値から算出してることになります。
S波速度の算出式を以下に列挙します。
・道路橋示方書
Vsi=100N1/3 (粘性土1≦N≦25)
Vsi=80N1/3 (砂質土1≦N≦50)
N値が0の場合はVsi=50m/sとしてよい
・建築(太田・後藤の提案式の修正式)
Advertisements
Vs=69・N0.17・(H/H0)0.2・Yg・St
H :地表面から層の中心までの深度(m)
H0:基準深度(=1.0m)
Yg:地質年代係数
(洪積層:1.3 沖積層:1.000)
H :深度(m)
St:土質に応じた係数
(粘性土1.0 砂質土・砂礫土1.1 礫質土1.4)
・建築(今井・殿内の提案式の修正式)
沖積粘性土についてはN値が0でもVsは値を持つので係数cを設定している。
Vs=a・Nb+c