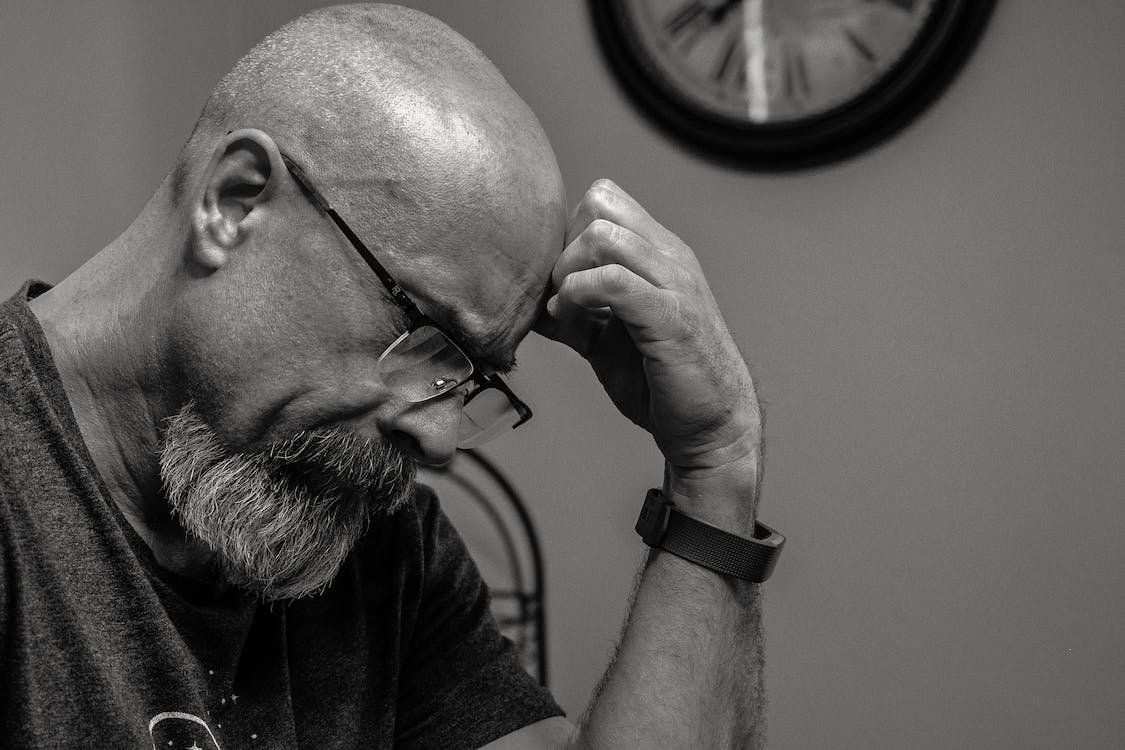
Advertisements
(1) 演繹法 演繹法は、簡単に言うと「○○だから、△△である」というように、論理を数珠つなぎにしていくものです。だれもが疑いようのない自明な公理から出発していき、論理を積み重ねることによって、複雑な結論にいたる方法です。 古代ギリシアの哲学者アリストテレスの思考法ともいわれ、その論法は3段論法とも言われます。
例1 大前提:すべての人間は死すべきものである 小前提:ソクラテスは人間である 結論 :ゆえにソクラテスは死すべきものである
例2 大前提:2で割り切れないものは奇数である 小前提:33は2で割り切れない 結論 :33は奇数である
さらに、演繹法における他の例を挙げてみましょう。
例3 大前提:すべての哺乳類は母乳を与える 小前提:猫は哺乳類である 結論 :猫は母乳を与える
例4 大前提:すべての鳥は翼を持つ 小前提:カナリアは鳥である 結論 :カナリアは翼を持つ
(2) 帰納法 帰納法は、「○○Aは××の性質である、○○Bも××の性質である、・・・、○○Xも××の性質である、→ おそらく○○には××の性質があるようである」というように、多くの観察事項(事実)から類似点をまとめ上げることで、結論を引き出すという論法です。
Advertisements
例1 観察事項1:「東京都民の平均年収は高い」 観察事項2:「神奈川県民の平均年収は高い」 観察事項3:「大阪府民の平均年収は高い」 →結論(一般論):「大都市圏の住民の平均年収は高い」
さらに、帰納法における他の例を挙げてみましょう。
例2 観察事項1:「A君は数学が得意だ」 観察事項2:「Bさんは数学が得意だ」 →結論(一般論):「数学の得意な生徒は多い」
例3 観察事項1:「この店の料理が美味しい」 観察事項2:「あの店の料理も美味しい」 →結論(一般論):「このエリアのレストランは料理が美味しい」
(3) 弁証法 弁証法とは、ドイツの哲学者ヘーゲルが考えたもので、「世界や事物の変化や発展の過程を本質的に理解するための方法」です。基本的には、物事には対立があり、それらを統合したより上位の概念が生まれていく、という過程を、「正(テーゼ)」「反(アンチテーゼ)」「合(ジンテーゼ)」という言葉を用いて説明しています。
例1 (正)花は美しい。 (反)花でないものは美しくない(花はいつか枯れる) (合)枯れた花は実を残す→「美しい花が実を残す」
例2 (正)少子高齢化が進行しているため、若者の政治参加を促すことが大切。 (反)若者は社会経験に乏しいため、社会にある政治的利害の対立を正しく導けない。 (合)教育制度を整えて若者の社会意識を高めることで、社会を健全化していく必要がある。
これらの方法を使って、論理的な推論を行うことが重要であり、正確な結論を導くためには適切な事例や事実を選び取ることが求められます。また、演繒法、帰納法、弁証法はそれぞれ異なる特性を持ちますが、大局的な思考において相補的な役割を果たす重要な方法論です。


