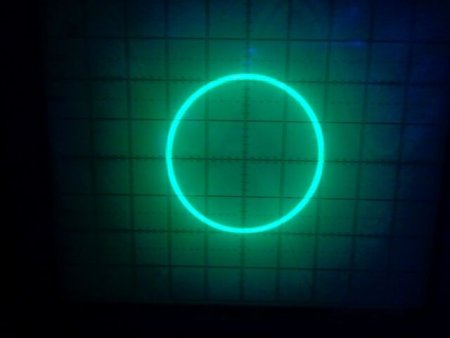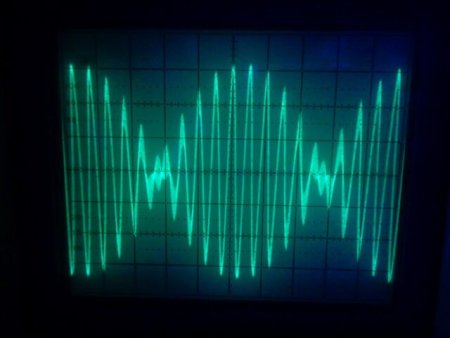Advertisements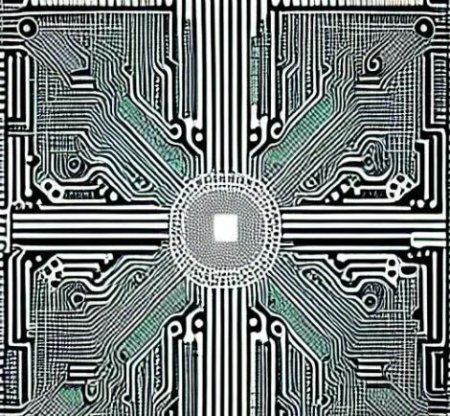
今回は此れに 39.3~39.8MHzを足して 50.0~50.5MHzを作る算段です。
得意な Si5351aを使って上記の周波数帯をつくり、これまた得意なダイオード DBMを使えば朝飯前の仕事?です。
少し心配なのは 40MHz前後で使った場合の Si5351aのスプリアス特性です。
半年程前に 39MHz以下で実際のトランシーバの VFOで使った時はスプリアスが -50db以下でしたが今回はどうでしょう?
そして Si5351aの CLK0--CLK2間のアイソレーション問題があります。
此方はイザトなれば2個の Si5351aを使えば良い訳ですが・・・
と云う訳で取り合えず 39.3~39.8MHz間のスプリアス実験をしました。
結果は否・否・否です、特に 40MHzに近づくと悲惨です。
余りの酷さに確かな数値を忘れました。「え~、此処に DDSVFOを使うのか~」 ヤダよ~です。
やはり 40MHzに近づくと此の発振器は使いモノにならないか!
でも 20MHzまでは高調波は出るけど、ほぼ完璧なのに
矩形波ゆえの奇数倍高調波は沢山出るけれど
う~ん、20MHzの第2高調波を使う手はないものか?
ウジウジしてても始まりません、此処は直ぐに実験します。
2逓倍に限定するならば(当に今回)ダイオードを2個使った共振回路を持たない両派整流型回路があります。
回路も簡単なので直ぐに実験しました。
でも基本波も含めて出力が殆ど出ません!
色々なダイオードを試しましたがダメです。
困り果てて、基本に戻って考えてみます。
其処で紙に両派整流型のマンガを鉛筆で書いて悩んでいました。
例のサインカーブの下側がダイオードの働きで上側と並んでポコポコ出る筈です。
・・・でも出ない、上側も出ない。何でだろう・・・
オシロで波形を見ても殆ど1本線です。
しかしオシロを繋いだ瞬間に其の1本線が激しく上下します。
何だこりゃと呟きながら直流レンジにして見ました。
すると見事な直流が観測されます。
此処でヤッとボケ爺さんが反応しました。
「此の回路は綺麗な矩形波で駆動すると直流が出力されるのだ~」
・・・いや、解ってしまえば当たり前ですがね!・・・
今更ローパスフィルタを入れるのは嫌ですから、Cxと云うコンデンサ1個で済ませたすったもんだ回路。
私的には大発見回路です。
因みに Cx値は実際の第2高調波レベルを見ながら調整しますが、かなりブロードです。
入力周波数にも由りますが今回は 470pFがベストでした。
後はお決まりの BPFを通り 2SK241で軽く増幅して 10mW前後にしています。